![]() 法律相談Q&A
法律相談Q&A
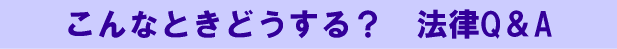
遺言・相続
| 状況説明 | |||||
| ■夫の相続 夫が1ヶ月前に亡くなりました。 夫名義の資産としては、自宅となっている土地・建物の他に、少しの預貯金があります。 夫は妻である私を受取人として生命保険を掛けていました。 遺族には、夫の母、私、長男、次男、孫がいます。 孫は、1年前に亡くなった長女の子供です。 |
|||||
| 質問と回答 | |||||
| Q1 | 今回の場合、誰が相続人となりますか。また、相続分はどのようになりますか。 | ||||
| A1 | まず、配偶者は常に相続人になりますから(民法890条)、亡くなったご主人の妻であるご質問者が相続人になります。 次に、子供も相続人になりますから(民法887条1項)、ご質問者の長男、次男が相続人となります。 また、長女が既にお亡くなりということですが、お孫さんがいらっしゃるようですので、お孫さんが相続人となります。 これを代襲相続といいます(889条1項)。 ご主人の実母(ご質問者の義理の母)ですが、この方は相続人にはなりません(民法889条1項)。 実親が相続人になれるのは、相続人に子供がいないこと、などの条件を満たす必要があります(民法889条)。 以上から、今回のケースでは、ご質問者、長男、次男、孫が相続人になります。 次に相続分ですが、配偶者と子供(代襲相続を含む)が相続人であるときは、配偶者に2分の1の相続分があり、子供に2分の1の権利があります。 子供が複数いる場合は、2分の1をさらに人数で割った割合が相続分になります。 今回のケースでは配偶者であるご質問者に2分の1の相続分があり、長男、次男、孫にそれぞれ2分の1をさらに3で割った割合、すなわち6分の1ずつの相続分があることになります。 |
||||
| Q2 | もし、夫に借金があることが分かって、自宅と預貯金の合計よりも借金の方が多い場合は、相続をしたくありません。どのようにしたらいいでしょうか。 | ||||
| A2 | 相続人は、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。 承継する権利義務には借金も含まれるとされています。つまり、マイナスの財産は相続しないが、プラスの財産は相続するということは認められていません。 ご質問のケースでは、自宅不動産と預貯金だけではなく、借金もあわせて相続をすることになります。 もし、不動産や預貯金で借金を支払い切れない場合は、相続人自身の財産で返済しなければなりません。 ですから、不動産と預貯金よりも借金の方が多い場合は、「相続放棄」の届出をすることで、相続をしないことも可能です。 相続放棄は、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に届出をしなければなりません。相続放棄の届出をすれば、借金だけでなく、不動産・預貯金というプラスの財産も相続することができなくなります。 なお、相続放棄をする前に、不動産を処分したり、預貯金を費消したりすると、単純承認をしたことになって(921条)、相続放棄をすることができなくなりますので、注意をして下さい。 相続放棄とは異なり、プラスの財産の範囲内で負債を相続する「限定承認」という制度もあります(822条)。 限定承認は、3か月以内に、家庭裁判所に(924条)、共同相続人全員で申立てなければなりません(923条)。 万が一、3か月以内に相続放棄や限定承認などの届出をしないと、自動的に単純相続、すなわちすべての権利義務を相続したことになりますので注意をして下さい。 |
||||
| Q3 | 夫は、受取人を私とする生命保険があるのですが、生命保険は相続財産に含まれるのですか。また、税金はどうなるのでしょうか。 | ||||
| A3 | 生命保険金は、保険契約によって保険会社から受取人として指定されている方が直接受領するものであり、相続財産にはなりません。 ですから、相続人であるご質問者が受取人となっている生命保険金は相続財産にはなりません。 仮に相続放棄の届出をしたとしても、生命保険金は受け取ることができます。 ただし、相続税の関係ではいわゆる「みなし相続財産」となりますので、課税の対象となります。 |
||||
| 2008/7/2 酒井雅弘 | |||||